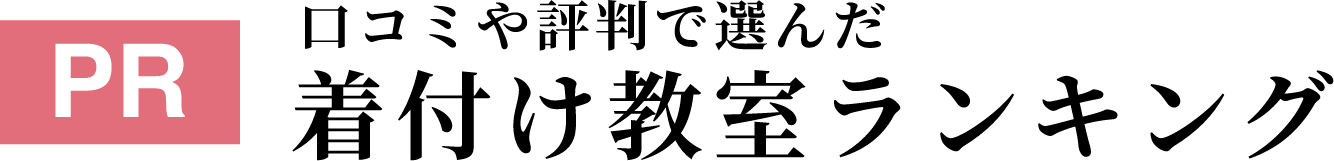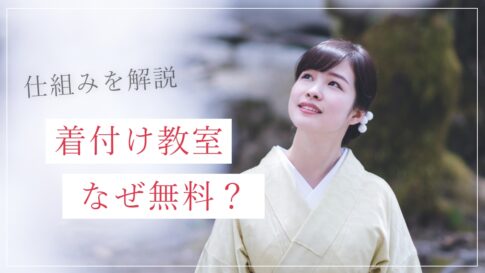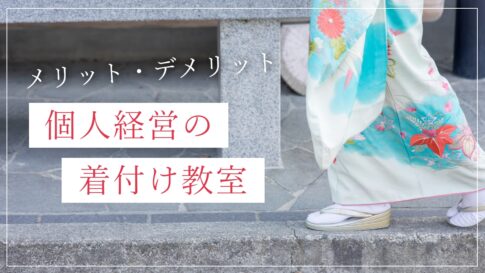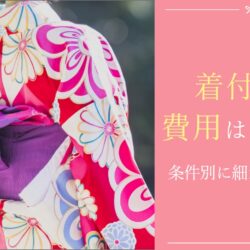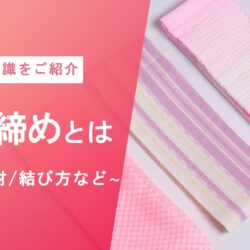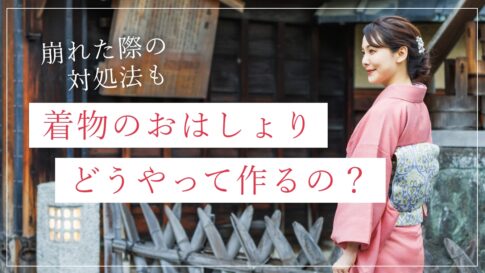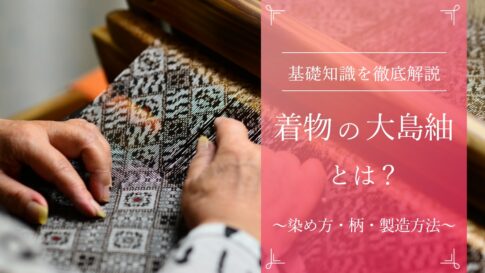着物の着付けに欠かせない「半襟(はんえり)」。
名称は知っていても、役割や合わせ方を知らない方は多いのではないでしょうか。
本記事では、半襟の役割や種類・場面別の選び方などを解説します。
半襟について詳しく知りたい方はぜひ最後までお読みください。
本記事を読めば、半襟の基礎知識を学ぶことができます。
着物の半襟とは?

半襟とは、着物の下に着る長襦袢(ながじゅばん)につける襟のことを指します。
大きさは、幅が15cm~20cm程度、長さが100cm~110cm程度です。裏地はついていません。
半襟の役割
半襟は、着物や長襦袢の襟に汗・皮脂汚れがつかないように保護する役割があります。汚れやすいので、着物を一度着るごとに付け替えるのが一般的です。
また、半襟は汚れから守るためだけでなく、おしゃれを楽しむためのアイテムとしても活用されています。
柄のない真っ白な半襟から、おしゃれな柄・色の半襟、レース・ビーズ付きの半襟までさまざまな種類があり、コーディネートを楽しめます。
半襟の歴史
半襟は、安土桃山時代に発祥し、結髪が普及した江戸時代に一般的になりました。
結髪には多量の髪油が必要とされていたので、襟元の汚れを防ぐためには欠かせないアイテムだったのです。
汚れの保護が目的で広まったものなので、色は汚れが目立ちづらい黒色が主流でした。
半襟がおしゃれ目的で流行しだしたのは明治時代・大正時代です。
日常的に着物を着ていた当時の女性にとって、半襟はおしゃれに欠かせないアイテムとなっていました。たくさんの半襟専門店が開かれ、どの店も非常に繁盛していたようです。
伊達襟(だてえり)との違い
伊達襟とは、着物を重ね着しているように見せるための襟のことです。重ね襟(かさねえり)とも呼ばれます。
大きさは、幅が10cm~12cm程度、長さが120cm~130cmです。半襟とは異なり、裏地付きで二重仕立てとなっています。
また、伊達襟は着物に必ずつけるアイテムではありません。この点も半襟とは異なります。伊達襟は、お祝いの場やおめでたい場で、「喜びが重なりますように」という願いを込めてつけることが多いです。おしゃれを楽しむ目的で使うこともあります。
半襟と伊達襟を確実に見分けたいときは、大きさを測ってみてください。
半襟の生地
半襟の生地にはさまざまな種類があります。本記事では、以下の代表的な6種類を紹介します。
- 塩瀬(しおぜ)
- 絽(ろ)
- 麻絽(あさろ)
- 縮緬(ちりめん)
- 絽縮緬(ろちりめん)
- 楊柳(ようりゅう)
1つずつ詳しく見ていきましょう。
塩瀬(しおぜ)
塩瀬は、袷(あわせ)の着物に用いる最も代表的な半襟の生地です。
細い生糸を密にした経糸(たていと)に、太い緯糸(よこいと)を平織りで打ち込んでいます。生地表面には横畝(よこうね)が現れています。
塩瀬を着用する時期は、初秋から春先までの10月初旬~5月末が一般的です。
絽(ろ)
絽とは、からみ織と平織という技法を混ぜ合わせて織られた生地のことです。
規則的に目(隙間)が空いているため、透け感があり通気性も良いのが特徴です。
暑い時期の6月上旬~9月下旬に使います。合わせる着物は、基本的には夏の着物である単衣(ひとえ)や薄物(うすもの)となります。
麻絽(あさろ)
麻絽とは、新潟県産の小千谷縮を麻素材用の染料で染めた生地のことです。
独特なシボやシワがあり、絽よりもさらに透け感があります。
特徴は通気性の良さです。素材が麻なので、吸水性・速乾性にも優れています。
7月初旬~8月末の盛夏に使用するのが一般的で、薄物に合わせることが多いです。
縮緬(ちりめん)
縮緬とは、表面に細かいシボがある生地のことです。
経糸に強く撚(よ)った緯糸を織り込むことでシボが生まれます。
特徴は、深みのある色合いと肌触りの良さ・重量感の3つです。
11月中旬~2月中旬の冬の時期に、袷の着物にあわせて着用します。
絽縮緬(ろちりめん)
絽縮緬とは、絽の技法で、縮緬の糸と織り方を用いて織った生地のことです。
絽のように通気性が良いですが、絽よりも透け感が少なく、縮緬のようなシボがあります。
着用する時期は、6月上旬~6月末と9月上旬~9月末が一般的だと言われていますが、7月・8月の盛夏に着用する方も多いです。単衣や薄物に合わせましょう。
楊柳(ようりゅう)
楊柳とは、縦方向にシボが入った生地のことです。経糸を強く撚ることでシボを生み出しています。
シボのおかげで生地が肌に密着しづらいため、サラッと涼しく着られます。
楊柳は、基本的には5月上旬~5月末や9月中旬~9月末に使います。単衣や袷の着物に合わせることが多いです。
半襟の生地は上記の他にもたくさんあり、季節や場面に合わせて使い分けることができます。半襟についてより詳しく知りたい方は、着付け教室で実践的に学びましょう。
半襟の選び方
半襟は、以下の3ポイントを基準に選びましょう。
- TPO
- 季節
- 着物の色・柄
順番に詳しく解説します。
TPOに合わせて選ぶ
半襟は、TPOに合わせて種類や色・柄を変える必要があります。
フォーマルな場面
フォーマルな場面には、白地に金・銀・白色の刺繍が入った塩瀬が合います。
例えば、結婚式や披露宴・卒業式・入学式・お宮参りなどです。
少しくだけた場面であれば、淡い色の刺繍が入った塩瀬を用いることもあります。
カジュアルな場面
カジュアルな場面では、色や柄が入った半襟を着用します。半襟の種類は問いません。
例えば、観劇やお食事会・同窓会・祝賀会などです。
着物に合う色・柄の半襟を選んでコーディネートを楽しみましょう。
季節に合わせて選ぶ
半襟は通常、季節ごとに使い分けます。以下の表を参考にしてください。
【半襟の季節一覧表】
| 塩瀬 | 絽 | 麻絽 | 縮緬 | 絽縮緬 | 楊柳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ◎ | – | – | ◎ | – | – |
| 2月 | ◎ | – | – | ◎ | – | – |
| 3月 | ◎ | – | – | – | – | – |
| 4月 | ◎ | – | – | – | – | – |
| 5月 | ◎ | – | – | – | – | ◎ |
| 6月 | – | ◎ | 〇 | – | ◎ | – |
| 7月 | – | ◎ | ◎ | – | 〇 | – |
| 8月 | – | ◎ | ◎ | – | 〇 | – |
| 9月 | ◎ | 〇 | – | ◎ | ◎ | |
| 10月 | ◎ | – | – | – | – | – |
| 11月 | ◎ | – | – | ◎ | – | – |
| 12月 | ◎ | – | – | ◎ | – | – |
着物は、季節に合わせて以下のように着分けます。
- 初秋から春先まで(10月初旬~5月末):袷の着物
- 初夏から初秋まで(6月初旬~6月末・9月初旬~9月末):単衣の着物
- 盛夏(7月初旬~8月末):薄物の着物
季節ごとに着物と半襟を着分け、コーディネートを楽しみましょう。
着物の色・柄に合わせて選ぶ
格式高い場面でなければ、半襟の色や柄は自由に選ぶことが可能です。
着物の色や柄が派手な場合、落ち着いた色や柄の半襟を選ぶと全体が引き締まって見えます。
反対に、着物の色や柄が控えめな場合は、派手な色や柄の半襟がアクセントとなります。
レースやビーズ付きの半襟などもあるので、着物の雰囲気に合わせて選んでみましょう。
カジュアルな場面における半襟の選び方に明確なルールはないので、気に入った半襟を選ぶのが一番です。
半襟の付け方
長襦袢に半襟をつける方法は、以下の3つが代表的です。
- 手縫い
- 安全ピン
- マジックテープ・ファスナー
それぞれ詳細を紹介します。
手縫い
半襟を手縫いでつける手順を紹介します。
- 半襟
- 長襦袢
- アイロン
- まち針
- 縫い糸
- 縫い針
- 襟芯
- 半襟にアイロンをかける
- 半襟の中心にまち針を刺し、長襦袢の背中心に合わせる
- 中心から端に向かって、まち針をとめる
- 縫い針に縫い糸を通す
- 半襟の上から2mm程度の部分を、端から約5cm間隔で縫っていく
- 端まで縫い終わったら、玉留めをする
- 長襦袢を裏返す
- 長襦袢の襟の幅に合わせて、半襟を内側に折り込む
- 中心から端に向かって、まち針をとめる
- 半襟の上から2mm程度の部分を、端から約5cm間隔で縫っていく
- 中心から半径10cmの範囲は、まつり縫いで縫う
- 端まで縫い終わったら、玉留めをする
- 襟芯を差し込んで、完成
半襟は、基本的には手縫いでつけることが多いです。特にこだわりのない方は上記の方法でつけましょう。
半襟の付け方については、着付け教室で教わることができます。やり方に不安が残る方は通うことも検討してみてください。
安全ピン
半襟を安全ピンでつける方法を紹介します。半襟をすぐに外したい方や、毎回付け替えたい方におすすめの方法です。
- 半襟
- 長襦袢
- 襟芯
- 安全ピン(15個程度)
- 長襦袢の地襟の中に、襟芯を差し込む
- 半襟の中心を長襦袢の背中心に合わせる
- 長襦袢の襟の幅に合わせて、半襟を内側と外側の両方に折り込む
- 長襦袢の表側から安全ピンを差し込み、表裏すべての半襟・長襦袢・襟芯をすくいあげてとめる
- 中心から端に向かって、安全ピンをとめていく
- 端まで留め終わったら、完成
手縫いが苦手な方でも簡単に半襟をつけられます。
また、手縫いよりも時間がかからないため、気分に合わせて気軽に半襟を付け替えることもできます。
マジックテープ・ファスナー
ここまで紹介した方法で半襟をつけるのが面倒だと感じた方には、マジックテープ付きの半襟や、ファスナー付きの半襟をおすすめします。
半襟自体にマジックテープやファスナーがついているため、簡単に半襟の付け外しができます。この半襟は長襦袢とセットで販売されていることがほとんどです。
色や柄の種類は限られてしまいますが、とにかく半襟を手軽に付けたい方に向いています。
半襟のお手入れ方法
半襟をお手入れするには、半襟を長襦袢から外す必要があります。手縫いの場合はハサミで縫い糸を切って、半襟を取り外しましょう。
取り外した後のお手入れ方法は、半襟の種類によって異なります。
塩瀬以外の正絹の半襟は、自宅で洗うと縮む恐れがあるため、クリーニング店に持ち込みましょう。
刺繍が入っている半襟はほつれてしまうリスクがあるため、着物のプロへの依頼をおすすめします。
正絹の塩瀬と、化学繊維の半襟の洗い方は次の通りです。
正絹の塩瀬のお手入れ方法
正絹の塩瀬は、手洗いでお手入れができます。
- たらいやバケツに水を入れ、中性洗剤を溶かす
- 1の中に半襟を入れ、約8時間漬け置きする
- 水に溶かした中性洗剤を歯ブラシにつけ、汚れが目立つ部分を優しくこする
- 汚れが落ちたら、水で半襟をすすぐ
- 手で半襟を絞り、陰干しをする
- 半襟が半乾きしたら、布目に沿ってアイロンをかけ、完了
自宅で手洗いをするのが不安な方は、クリーニング店に持ち込んだり、着物のプロに依頼したりするのも一手です。
化学繊維の半襟のお手入れ方法
化学繊維の半襟は、洗濯機の弱水流で丸洗いできます。長襦袢の素材が化学繊維であれば、半襟を外すことなく洗濯することも可能です。
なお、脱水は洗濯機で行ってはいけません。シワがつく恐れがあります。
洗濯した半襟は手で絞り、陰干しで乾かしてください。
半乾きの状態になったら、布目に沿ってアイロンをかけ、お手入れは完了となります。
まとめ
本記事の内容をまとめるとこのようになります。
- 半襟とは、着物の下に着る長襦袢につける襟のこと
- 着物・長襦袢の汚れ防止や装飾の役割を持つ
- 半襟には、塩瀬や絽・楊柳などさまざまな種類がある
- 半襟は、「TPO」・「季節」・「着物の色や柄」によって使い分ける
- 長襦袢に半襟をつける方法は、「手縫い」・「安全ピン」・「マジックテープやファスナー」の3つが代表的
- 正絹の塩瀬と化学繊維の半襟は自宅でお手入れ可能
- 上記以外の半襟をお手入れする場合はプロへの依頼がおすすめ
本記事の内容を基に、半襟のコーディネートを楽しんでみてください。
この記事が、着物の半襟について知りたい方の参考になれば幸いです。